2021年10月、米プリンストン大学の真鍋淑郎上席研究員がノーベル賞物理学賞を受賞しました。明るい題材の乏しい日本において、MLBの大谷選手と並んで海外で活躍する日本人の偉業達成は、本当に明るいニュースだとみなさんも感じたことでしょう。
日本人ノーベル賞受賞者は、2001年以降の南部陽一郎(米国籍)、中村修二(米国籍)を含め、19年の吉野彰、今回の真鍋淑郎の受賞で19人を数えます。米国の60人を超す受賞者数は別格としても、2020年に日本人の受賞者がいなかったことを除けば、21世紀になって日本人の受賞者数はほぼ毎年で世界第2位となり、欧州(英独仏など)を上回っています。
しかも自然科学分野においては、基礎科学から応用工学までじつに幅広い分野で受賞している事実は、停滞している日本経済や低迷している日本社会のことを勘案すればむしろ驚くべきことです。
ノーベル賞の受賞者数の多い国の上位10位(2021情報)までを国別で見るとアメリカが断トツ(388人)の1位で、以下イギリス(133人)、ドイツ(109人)が上位3カ国と、そのほかもほとんどが欧米諸国です。日本は7位(28人)と非欧米諸国のなかではもっとも多く、もちろんアジアでは唯一トップ10入りしている国です。
真鍋研究員が、「最も面白い研究とは、好奇心が原動力になった研究だ」と、受賞後の記者会見で日本の若手研究者にむけてメッセージを送りました。「好奇心」という言葉をくり返すほど、その大切さについて語っていたことが私にはとても印象的でしたし、多くの人が同じように感じたことでしょう。
「好奇心」ーーこのありきたりのようでありながら大切な言葉。今回、それについて述べようと思います。この記事を読んで、もし好奇心についてあらためて考えるきっかけ、あるいはなにかの気づきやヒントにでもなればとても嬉しく思います。
ビジネスにおける好奇心の重要性、ビジネスマネジメントとの関係

好奇心については、あの経営学誌『DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー』でも、2018年12月号で「特集:好奇心 組織の潜在力を引き出しビジネスを成長させる」という号を発行しているほど。
フランチェスカ・ジーノ教授は、ハーバード・ビジネス・スクールではもっとも注目を集めている一人です。同教授は、好奇心が企業業績にはたす役割が、これまで考えられていたよりもはるかに大きいことを数多くの実証研究により証明しています。
ジーノ教授の論文「好奇心を収益向上に結び付ける5つの方法」(原題:The Business Case for Curiosity)は、同教授とほかの研究者たちとによる企業事例をもとにした研究成果で、企業における好奇心の恩恵やその発揮方法、阻害要因などを分析し、従業員だけではなくリーダー(マネジメント層)の好奇心を刺激しながら業績向上のための5つの方法を提言しています。
3,000人を超えるジーノ教授による独自調査の結果では、好奇心旺盛な人の92%はチームや組織に新しい発想をもたらすとし、好奇心は仕事への満足、モチベーション、イノベーション、そして高業績につながると考えていると返答しています。
その一方で、「仕事をしているとたびたび好奇心が沸いてくる」という人は約24%にしかすぎず、70%ほどが職場では個人的に好奇心をもつことは気が引けるので抑制していると回答。
つまり、「好奇心」に満ちた組織つくりは、米国の企業経営においても重大な要素と認識しているにもかかわらず難しいテーマであることがわかります。
好奇心を阻害する2つの要因
企業において従業員の好奇心を阻害してしまう要因ついて、論文では2つの点があげられています。
第1に、組織のリーダーは、「従業員に個人的な関心の追求を認めると、会社をマネジメントにくくなる」と。つまり、マネジメントに混乱が生じ、それを避けるべきだと考えているのです。イノベーションを口にはしていても、革新的なアイデアを提案されるとそれを退ける判断をくだすことが多いという現実が、多くの企業事例に関する研究で証明されています。
第2には、企業が効率性や合理性を追求する傾向が顕著になっていることが理由です。それというのも、個人的な好奇心が意思決定の遅れと業務の混乱、事業コストの増大、さらには市場機会の損失につながるのではないかと懸念し、好奇心を抑制する決断を下しているからです。
好奇心を解き放つ5つの方法

ジーノ教授の論文では、マネジメント層や従業員の好奇心を醸成あるいは育成するために、以下の5つの方法を提案しています。
(1)好奇心旺盛な人材の採用
グーグルでは好奇心が旺盛な人材を発掘するため、面接で「未知の何かを学ぼうとして寝食を忘れるほど没頭した経験はありますか。それはなぜですか。」といった質問します。元CEOのエリック・シュミットは「グーグルの経営において重要なものは、答えではなく、問い」なのだと発言しています。
(2)探究心や知識欲を発揮して範を示す
リーダーは、一般的に部下に語りかけることが大切だと考えがちです。しかし、それは見当違いだと。質問を投げかけることが、むしろ効果的であると研究成果から導き出しています。
他者の意見やアイデアに関する質問を投げかけることで、みなが触発されてより深く考えることで好奇心を持つようになると。
(3)学習目標を強調する
企業は、どこでも成果を重視します。しかし成果偏重より、学習を重視するほうが個人と組織の両方にとっては有益であり、それはいくつかの研究成果が裏づけていると述べています。
(4)興味関心の対象を広げて探求するよう、従業員の背中を押す
業務外の興味関心を後押しするために、自社のリソースを提供する企業があります。
1990年代ピクサーが本社を移転するにあたり、当初は部門ごとに別棟を設ける計画でした。しかし、ジョブズは部門間での隔たりが生じるとし、全部門を一棟にまとめ従業員同士が交流しお互いの仕事やアイデアを交換することで、興味や関心を高めることができたのです。
(5)「なぜ」「どうすれば」という疑問をぶつける日を設ける
すぐれた質問をする術を教えることは、部下たちの好奇心を引き出すことに役立つと、MITのボブ・ランガーは語ります。
また、上記のジーノ教授の論文が掲載されている同誌の特集号の巻頭では、ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正の「世界で勝ち抜くには好奇心が不可欠である」と題されたインタビュー記事が掲載されています。
そのなかで、日本人ビジネスパーソンの好奇心の弱さ(希薄さ)、興味や関心対象の狭さを問題にしています。それは、情報が偏在し多様性にも乏しい企業の組織体制に加え、新しいことを学習する環境、そうした経験をしようとしない個人の傾向という両方に問題があると指摘しています。
そしてここでも「なぜ」と繰り返すことが、好奇心を引き出すあるいは育むことにつながると語っています。
この特集号には、そのほかにも「好奇心の5つの類型」、「リーダーの成功と好奇心の関係」、「ヒトもAIも好奇心で進化する」など、企業、マネジメント層、従業員などのビジネスにおける好奇心の参考となる論考もあわせて掲載されています。
埋もれているかもしれない「宝物」ーー好奇心

私自身は、好奇心・独自性・洞察力の3つをとても大切にしていることはこれまでにも幾度か述べてきました。そのなかで、好奇心こそが鍵になると判断しています。
それというのも、独自性は偶然に発見するか意図的に創出しなければなりません。洞察力は、知見の蓄積と思考力を鍛えることが必要でそう簡単には身につきません。
しかし、好奇心をもつことはだれにとっても難しいことではなく、しかも何にたいしてもそれを持つことができるからです。
幼児は見るもの経験すること何にでも好奇心を示します。その姿勢は大事に育てるべきですし、好奇心があれば想像力がよく働き、そして創造力も養われるからです。わたしたちも最初はみな幼児と同じはずだったのですが、成長し年齢を重ねるほどに残念ながらそれは少しずつ失われあるいは衰えていくのです。
ビジネスにおいて、業務経験が豊富になるほど好奇心が薄れていくとジーノ教授も述べています。
真鍋淑郎上席研究員が記者会見で好奇心の大切さや必要性について語っていたのは、彼自身がそのことを十分に実感しているからこそでしょう。何かを成し遂げる人たちは、きっとみな好奇心にとりつかれているからです。
好奇心、それを一生持ち続ける人は稀です。
だからこそ、第三者からすれば取るに足らぬほど些細なことであれ、本人が好奇心をもてる対象があるならばそれは宝物となります。
いつ、どこで、何をしているとき、じっくりと考えることが出来るのかという設問に、仕事を離れた時間や空間と、ほぼ全員が答えていることにも驚きはありません。
企画やアイデア会議でよい案が浮かばなくても、その後の慰労を兼ねた懇親(飲み)会で良い意見やアイデアが浮かぶことは、だれしもがおそらく経験していることです。
米国の3Mの「15%ルール」やグーグルの「20%ルール」など、個人的な好奇心をそうした時間に向けることをうながす企業文化があります。
オフィス環境のデザインも単に効率的なデスクの配置より、社員同士が寛いで交流しながらコミュニケーションを活性化し、お互いの興味や関心が交配させることで新しいアイデアの発見、イノベーションにつなげることができる環境が重要なことも認知されています。
フランスのカフェ文化が「芸術の街パリ」を生んだことは知られています。つまり、社会学者のレイ・オルデンバーグのいう「サード・プレイス」=第三の生活空間を、仕事場に意図的につくり出す工夫をすることが大きな意味を持っています。
好奇心、その先につながるものとは
いま思い返してみれば、どうしてあれほど夢中になったのかというようなことはあるはずです。それは、おそらく遠い記憶の彼方であっても、そうした経験は誰にもあるにちがいありません。それも好奇心の賜です。
何かについて好奇心がうまく発揮されれば、こだわり(執心)、没頭(熱中)に結びついて、やがては探究(研究)心にまで発展します。さらに極めれば、それは創造性や独自性の創出となる可能性をも秘めているのです。
好奇心が高じ、それはやがて趣味となった人もいるでしょう。趣味というのは、その人がもっとも充実している時間のすごし方です。日ごろの業務や雑事、ストレスからも解放され、そのことに集中あるいは没頭できる濃密で至福の時間です。
さらに好奇心でえた知見は、副(複)業のきっかけ、それもプロボノなど社会的な意義のある貢献になるかもしれません。それがひいてはキャリアアップだけではなく、ひょっとして好奇心から思いがけない人と出会い、そこから違う仕事や職業を選ぶことになるかもしれません。
好きで始めたことのはずのことが、思いもかけず様々なチャンスや可能性へと広がることもあります。
そうした視点で考えたとき、好奇心を持つか持たないかというのは、その人にとって人生を左右するほどの課題だと判断しても、言い過ぎにはならないだろうと。
すさまじいスピードで技術革新が進展しつつある今日、好む、好まざるにかかわらず、ビジネスから人びとのライフスタイルまで大きく変えつつあることは、日常生活のなかでだれでもが実感しています。
デジタルテクノロジーの進展が私たちの生活を変えつつあることを認めざるをえないですし、それとは別の意味で好奇心が生活を変えるということに気づくはずです。
ビジネスの源泉としての好奇心——マーケターに求められていること
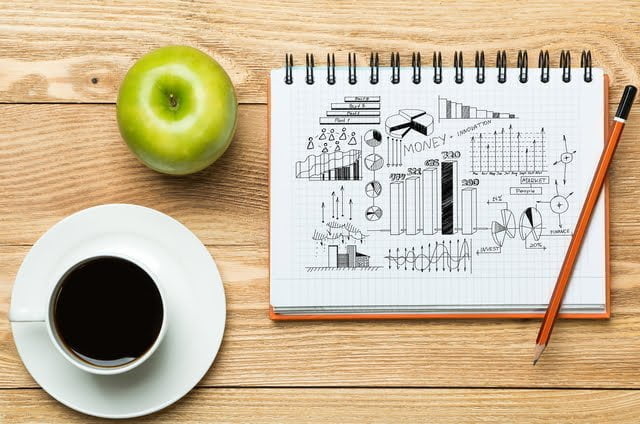
職種や業種を問わず、「すべてのビジネスパーソンが好奇心を持つ必要性がある」、と断言できるだけの知見は私には残念ながらありません。
マーケティングが重要だと認識されている今日。それは、もはやマーケターだけが担っていればすむものではないのです。
3年前、私が「マーケティング「思考」とマーケティング「マインド」について考える」で述べたドラッカーとHPの創業者デビッド・パッカード、この二人のすぐれた洞察による名言を思い起こす人もきっと多いにちがいありません。
企業人であれば、だれでもがマーケティングマインドあるいはセンスをもつ必要性がありますし、今後もそうした傾向は強まることはあれ弱まることはありません。
全員のマーケティングマインドが難しいとしても、マーケターだけは世の中のあらゆる変化または兆候をつねに鋭敏に感じ取り、それらを迅速にマーケティング戦略に反映させることが要求されています。
そうした姿勢や心構えが、新製品やサービスの開発はもとより、社会や消費者からの評判や評価、支持や共感の獲得、好感度や信頼を醸成するのに効果的なコミュニケーション施策として実施できるようになるのです。
なかでもPRパーソンは、あらゆるモノ・ヒト・コトがコンテンツに結びつき、社外・社内はもとよりあらゆる人たちにむけて全方位に情報発信し、ときに必要に応じて密接なコミュニケーションによる接点構築をすべき立場にいるのです。
つまりPRパーソンこそ、だれよりも強く好奇心を発揮しなければならない職種なのだ、というのが個人的な経験としても実感していることです。
さて、みなさんはいま何に「好奇心」をお持ちですか?

