クリステンセン教授のこの最新刊、またも刺激に満ちています。8年と20年。前者は、同教授が破壊的イノベーション理論にかかった年月。後者は、本書のジョブ理論を精緻化するのについやした年数。
同教授の著書中、もっともマーケター向けの内容で、マーケティング関係者に限らずあらゆるビジネスパーソンが読むべき本だろうと感じます。
本書の原題は“Competing Against Luck”は、日本語でいえば「運頼み(任せ)に打ち勝つ」というような意味です。
教授には、イノベーションは幸運や偶然がもたらすものではない、という考え方があるからです。
クリステンセン教授の『イノベーションのジレンマ』(原題:Innovator’s Dilemma:When New Technologies Cause Great Firms to Fail)が発売されたのは1997年(原著)。
それから20年。同教授の破壊的イノベーションの考え方は、その後の経営・マネジメントだけではなく、マーケティング戦略から情報、組織・人材にいたるまで避けて通れないほどの影響を与えました。今日では同書は、とくに経営戦略やマーケティング戦略においてすでに“古典”ともなっています。
ちなみに、英国の著名コンサルタントらにより隔年で選出される「最も影響力のある経営思想家トップ50(Thinkers50)」では、2011、2013年と2度連続で選ばれています(ちなみに、2001年初回の第1位はピーター・ドラッカー)。
誤解されてきた破壊的イノベーション理論

これまで破壊的イノベーション理論は誤って解釈され適用されてきた、と教授は語ります。
クリステンセン教授がいう誤解とはこういうことです。
それまで優良といわれていた企業が、ほんの小さな兆しに過ぎないと見なしていたものが破壊的なイノベーションを引き起こしたとき、既存企業の判断や経営戦略と行動の誤りが、やがてはそうした破壊的イノベーション企業に遅れをとり、場合によっては市場(顧客)そのものを奪われる。かつては優良と讃えられていた企業が、なぜ対応できずに衰退し消えていってしまうかを説明する理論でした。
しかし、破壊的イノベーション企業が市場に登場すると、そうした新しく、野心的で賢い新興企業(とテクノロジー)であれば、それらはなんでもかんでも破壊的イノベーションだと拡大解釈されてきたというのです。
また、同理論は新しい市場をどこで発見すべきか説明しない、新製品・サービスをどのように生み出すのか教えてはいないし、どれが成功するのか予測することもないと。
しかし、この「ジョブ理論」では、それらすべてが可能でこれからのイノベーションを予測し、生み出すために書かれたのだと語ります。
「ジョブ理論」の“ジョブ”とは何か

正式には、「片づけるべきジョブ理論」=Job to Be Done(以下、ジョブ理論)というのは、顧客が製品やサービスを生活のなかに引き入れるのはあるジョブ(用事や仕事など)を片づけるためなのだが、その理由を理解することこそ重要で、そのためには相関関係ではなく因果関係に着目すべきでそこから始めなければならないし、この“なぜ”を理解できるか否か、それが運任せではないイノベーション正否の分岐点になると述べます。
冒頭にファストフード・チェーンの事例が語られます。同チェーン店では、どうすればもっとミルクシェイクが売れるのか。顧客プロフィールに基づきマーケットリサーチを行い、何度か新製品を投入してみたが変化がありませんでした。
そこで、まったく違う“切り口(視点や着眼点)”から課題へアプローチします。つまり「来店者の生活に起きたどんなジョブ(用事、仕事)が、彼らを店に向かわせ、ミルクシェイクを“雇用”させたのか」と。
その結果、現象としてみれば顧客が購入しているのはミルクシェイクなのだが、購入する人たちは「長いドライブの退屈しのぎ」や「子供に優しい父親の気分を味わうため」など、その理由はまったく千差万別・十人十色でした。
こうした現実世界の知見と積み重ねから、切り口変えること(思いもよらぬ視点)の意義と価値に気づいたのです。
こうしたことは、ドラッカーの「企業が売っていると考えているものを、顧客が買っていることは稀である。」(『想像する経営者』:原著1964年刊)という卓見、またセオドア・レビットの「4分の1インチ・ドリルがほしいのではない。4分の1インチの穴が欲しいのだ」(実際にはレオ・マックギブナのものだとレビット自身は語っています)という有名なマーケティング格言を象徴するエピソードです。
「何を」ではなく、「どう」考えるかの重要性

本書は、クリステンセン教授とほか3名の共同執筆で、3部構成・全10章立て370ページ余り。それは、何が顧客をしてその行為(購買行動など)をとらせるのか、それを真に理解することから始めるべきことの説明からはじまります。
<第1部>は、イノベーションに不可欠な因果関係のメカニズムについて、いくつかの事例を通じて「ジョブ理論」の概要が説明されます。
教授は、みな相関関係と因果関係が同じではないことはわかっていても、前者に安住してしまう。しかし、イノベーションで重要なのは、消費者が“なぜ”(根底の因果関係)ある特定の商品を買うのかを真に理解しなければならないと。
それには、「ジョブ理論」というレンズを通すことで、みなと同じものを見ても、違うように見えてくるのだと語ります。このレンズこそが、切り口(視点=着眼点・着想)なのです。
つまり、先述のドリルの例でわかりやすくいうならば、顧客の問題解決(穴を開ける)を提案することができれば、それはドリルでないモノでもかまわないという視点を持つことです。
なぜならば、顧客が本当に欲しいと思っているのは、商品そのものではなくその企業が提供する解決策だからです。
教授は、ジョブ理論について、これまでのデータや数字に頼るやり方に反するものだと断ったうえで、以下のように定義しています。
“「顧客はある特定の商品を購入するのではなく、進歩するために、それらを生活に引き入れるというものだ。この「進歩」のことを、顧客が片づけるべき「ジョブ理論」と呼び、ジョブを解決するために顧客は商品を「雇用」するという比喩的な言い方をしている。この概念を理解すれば、顧客のジョブを発見するという考え方が直感的にわかるようになる。」
ここでは、ジョブ理論の事例として、教育機関(サザンハンプシャー)、B to B(フランクリン・コヴィー社)、消費財メーカー(P&G)などが取り上げられ、適用範囲は広くて深いといいます。

<第2部>では、ジョブは発見するものであり、複雑で混沌とした現実世界(それは同時にありきたりな生活)のなかで、すぐ目の前にあるかもしれないジョブを見つけ出す以下の5つの方法(視点)をあげています。
(1)生活に身近なジョブを探す
(2)無消費者と競争する
(3)間に合わせの対処策
(4)できれば避けたいこと
(5)意外な使われ方
このパートで私が印象的なのは、マットレス購入のエピソードです。この日常的でありふれた製品の購入にいたる消費者へのインタビューです。
マットレス購入の場(状況)での購買行動だけを見れば、ある一人の衝動買いにしか見えないことでしょう。しかし、その根底にある複雑な感情でのゆらぎこそジョブ発見の糸口になるのです。
上記(2)の「無消費者」という言葉は、私もそうですがみなさんもはじめて耳にするのではないでしょうか。
「無消費者」とは、ジョブを不満足に片づけるくらいなら、むしろなにもしないという多くの人たちなのですが、それが実は宝の山であり、企業にとっては大きなチャンスだと。なぜならば、それは手つかずの市場だからです。
また、「意外な使われ方」というのは、(3)とも関連していますが、とくにイノベーティブな製品やサービスに限らず様々なモノに当てはまるでしょう。
これは企業が利用を想定して開発した製品やサービスを、その企業が想定もしていなかったやり方で消費者各自の都合や事情による独自の利用する方法のことですが、そうしたことこそはイノベーションの大きな機会であるということです。
教授は、ハーバード・ビジネス・スクールの脳科学(ニューロ)マーケティングのジェラルド・ザルツマンの見解、純粋な知見(インサイト)はそれが見つかった(体験した)瞬間に真だと気づくものだと語ります。
また、ジョブ理論は完全な科学ではないかもしれないが、変数から答えを導く公式などではなく、重要なのは複数の切り口(視点・着眼・着想)をもつことだとクリステンセン教授は付け加えています。
しかし、たとえジョブを発見してもそれは始まりにすぎず、ここから長い道のりが待っています。
新しい製品やサービスが成功するのは、それがもつ機能や性能自体がすぐれているのではなく、それがもたらす顧客体験がすぐれているか否かだと述べています。
そうした顧客体験を知ることができるのが多種多様なオンラインレビュー(ソーシャルメディア)で、買い物体験を大きく改善しすぐれた商品の発見や雇用を促す力があると。

マーケティングリサーチにおいて重要なことは、顧客に質問(インタビュー)することではなく、その声に耳を傾ける(傾聴する)こと。それというのも、消費者は自分の望み(かたづけるべきジョブ)について常に明確に答えられるとは限らないからです。
このジョブは顧客の立場から状況を組み立てるのに対し、今度はジョブスペックを把握します。
ジョブスペックとは、イノベーター視点からジョブをとらえ解決策の要件を把握するプロセスです。ここでは、顧客が克服すべき障害物(トレードオフなど)を機能だけではなく感情的・社会的側面から適切な体験構築を計画することです。
ジョブ理論によるイノベーションを他社が模倣できない理由のひとつは、このジョブスペックが詳細なことによると述べています。
そして究極的な競争優位性を得た製品・サービスを、教授はパーパス(目的)ブランドと呼んでいます。
私がこのパートで一番印象的なのは、米国ではバービー人形の人気を凌ぐといわれるほどになった「アメリカン・ガール」人形を提供するアメリカン・ドール社(現在はマテル社の傘下)のケースです。
人形だけではなく、人形を含めた顧客体験が同社の成長を支えているのです。同社の創業者プレザント・ローランドは以下のように語っています。
“「あのころ、プロダクトに体験を深く落とし込もうとする人はいなかったと思う。多くの人にとって人形は商品にすぎなかったし、ストリーづくりのたいせつさも理解されていなかった。」”
この言葉は、Machintosh、iPhoneなどのアップル社も同様で、製品の機能や性能、筐体デザイン、UI/UXなどはすぐに模倣できても、その製品と一緒にもたらされる顧客体験とそれを提供し続けるだけの組織と人材は、そう簡単には真似できないことからも理解できるでしょう。
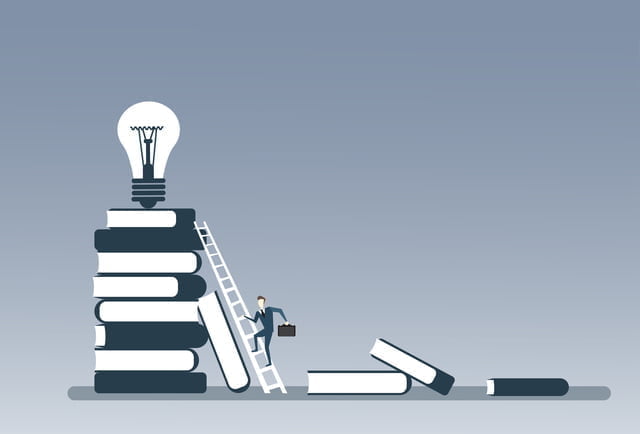
<第3部>は、ジョブを発見し、新しい製品やサービスを開発できても、それをイノベーティブなものとし、他社に競争優位性を発揮するには組織や人材まで含めた一連のプロセスまでも構築しなければならないと強調しています。
イノベーティブな企業は、顧客の片づけるべきジョブ中心の組織に最適化し、容易に競争相手が模倣・追随できない独自のプロセスに進化させ、それを競争優位性の原動力としていると。
なぜならば、製品やサービスは簡単に模倣されてしまうが、組織全体のプロセスまでは簡単には模倣できず、それこそが真の意味での差別化であり容易に競争相手が追随できないことだからです。
ジョブ中心にプロセスをつくりあげることの意義と価値はわかっても、ほとんどの企業にとってたやすいことではありません。
どの企業にも培ってきたプロセス(伝統)があり、それらは効率をあげるための業容あるいは職能や機能別による事業部、地理的条件などで決められます。
そして、サイロ(硬直)化した組織に馴染んでいることは、居心地がよく狭い範囲での成果で満足してしまうからだと言い切ります。
そのためには、ジョブに基づいた体験を提供し、その体験を供給し続けることをミッションに企業を組織することが、破壊的イノベーター(競争相手)への一種の予防接種(対抗処置)的な働きと効果をもたらすことができ、それこそが真の意味での差別であり競争優位性を確保することができると語ります。
このパートでは、様々な企業がジョブ中心の組織をどのようにして構築しているのか、豊富な企業から、それぞれがどのようにしてジョブ中心の組織としているのかが具体例を通じて紹介され、実際にどのように進めるべきなのか読者にはわかりやすく伝わり、多くの示唆が得られることでしょう。
ただし、クリステンセン教授は、このジョブ理論といえども万能薬ではないと最後の章で下記の3つのポイントで注意を促しています。
第1にジョブ理論でイノベーションは運任せではなくなること、第2にジョブ理論の限界を知ること、第3に本書が読者の好奇心を刺激することです。
クリステンセン教授は、ジョブ理論があたかもすべてを解決する公式や方程式のような誤解を与えないか。さらに、ジョブ理論で説明できない状況をみなさんが発見してくれたら嬉しいとも語っています。

ところで、本書を読んで私が思い出したのは、2010年の「頭のいい人も新事業で大ゴケ!?事業創造のサイエンスとは」というテーマのセッションのことです。
これは、サイボウズ創業者の高須賀宣さんを招き、新製品開発や新規事業を出すときにブレストのようにアイデア量に頼るのもロジカルで導かれたアイデアも共に駄目で、飛躍的なイノベーションは同じ枠組み内で考えるのではなく、まったく別の視点から考えることが良いイノベーションやアイデアを出すためのキーになり、成功の確立を高めることだと語ったのです。
そのときの感想を「着眼・着想と気づき・ひらめきはセットである。」と私は書きましたが、本書を読みはじめてまず頭に浮かんだことで、高須賀氏の話の内容と共通するものあると感じました。
しかし、この視点・着眼点・着想を変えるというのは、刑事ドラマなどでも視点を変えることで事件解決の糸口を発見することがありますが、時間を要して高度な知識やテクニックを身につける必要もなく簡単なようで「言うは易く行うは難し」でしょう。
なぜならば、新製品・サービスを開発するさい、単に新しい“なにか”機能を追加することではなく、まずは切り口を変えて感情面・社会的な側面にまで深くかつ多面的に考慮する必要があるからです。
クリステンセン教授も、ジョブ理論構築のために、機能以上に感情的・社会的側面のもつ複雑な多層性について身をもって知ったあと、多種多様な業種、数多くの企業のケースを探求(研究)し、この新しいフレームワーク構築には長い年月が必要でした。
本書は、同教授の『イノベーションのジレンマ』以降20年にわたる畢生の成果であり読む価値はあると私は感じました。


