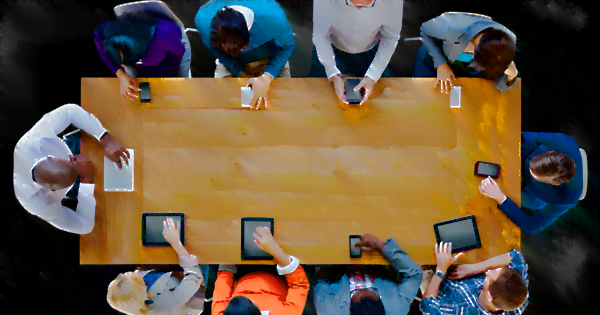マーケティングコミュニケーション関係者に、これまでの著書の中でどれか1冊だけすすめるとしたら本書です。
豊富な事例、ちりばめられたヒント、深い洞察(予見)、刺激的な示唆(提言)など、ヒントの詰まった深い内容で、読むその人によって気づき、確認、確信を与えるでしょう。
本論だけで全420ページ余り、その前には東京工芸大学講師の茂木崇、東洋経済オンライン編集長の山田俊浩、朝日新聞メディアラボの井上未雪の3名による本書の解説、ジェフ・ジャービスの紹介、推薦文などが30ページあります。
それらを読むだけでも、ジャービス本人の語る言葉に耳を傾けたくなるでしょう。
デジタル、ソーシャルメディア、スマートフォンの“日常化”が、それまでの20世紀的なあらゆる産業、ビジネス構造そして社会生活(コミュニケーション、ライフスタイルから教育まで)までも根本的に変えてしまいました。
そしてさらに、これからも多様に変化し続ける環境から私たちは逃れることはできません。
メディアやジャーナリズムの危機が喧伝されるようになってから久しく、ここ数年はそうしたメディア状況に関する書籍も国内外の著者から数多く刊行されています。
メディアや情報と私たちのかかわり方については、2012年にイーライ・パリサー著の『閉じこもるインターネット』(現ハヤカワ・ノンフィクション文庫版『フィルターバブル〜インターネットが隠していること』)がずいぶんと話題となり、読んだ人も多いでしょうし私も書評(セレンディピティや多様性が失われ、「類は友を呼ぶ」だけの世界になってしまうのか?ーー『閉じこもるインターネット』を参照)で取り上げました。
さて、2年前(2015年)、こうしたメディア事情に関するセッション(参照:「注目すべき海外先進メディアとトレンド最前戦」に参加してーーメディア”感覚”とその未来について思う」を参照)が開催され参加しました。
当日のパネリストたち(3名)が、いわゆる“レガシー”メディア関係者ではなくいずれも若い編集者たちだったことがとくに私の関心を引き、そのセッションについて以下のように述べました。
「デジタルネイティブ世代がライフスタイルを満喫するには、テレビや新聞などのメディアはもとより、ホームページもEメールも必要ではなく、すべてがスマートフォンだけで十分だという意識なのだ。
メディア環境が変化するのがあたり前の中で成長してきた彼らにとって、メディアは常に変わり続けるものであるという自明の意識(前提)があるのかもしれない。あるいは、こういう視点があるかもしれない。
それはメディアとジャーナリズムは常に対だと考えている人たちとは違う感覚だとしたら、それらの将来をどのようにとらえているかという問題だ。」
メディア業界は、ステマ、ネイティブ広告(スポンサードコンテンツ)、加えて昨今ではフェイクニュースという新たな問題も抱えており、本書の目次をながめただけでもマーケター、とくにPR関係者やソーシャルメディア(コミュニティ)運営者たちは“そそられる”ことでしょう。
メディアやジャーナリストたちとのつながりも深く、これからのメディアのあり方や方向性についてどのように変わっていくのかけっして等閑に付すことはできず、したがってこのテーマに無関心でいることはできません。
信頼の高いジャーナリストのジェフ・ジャービス

ジェフ・ジャービスの高名は知っていたのですが、彼の著書を読むのは実は本書が初めてです。
ジャービスは、ニューヨーク市立大学大学院ジャーナリズム学科教授で、これまでにも『グーグル的思考』、『パブリック〜開かれたネットの価値を最大化せよ』など、日本でも話題の著書で既知の人も多いでしょう。
ジャーナリズムの未来、メディアとコミュニティとの新たな関係などについての論客として知られ、また、インターネットとメディアをテーマにしたブログメディアの中でも高い人気と信頼を誇る「Buzzmachine.com」の運営、英国「ガーディアン紙」のアドバイザーでメディアに関するコラムも執筆しているほどです。
さらに、起業ジャーナリズム・タウ・ナイト・センターを設立し所長に就任。2007年度と2008年度の「世界経済フォーラム(通称:ダボス会議)」では、「世界のメディア・リーダー100人」の1人に選出され、「エンターテインメント・ウィークリー」誌の創刊と初代編集長も務めたことでも知られ、デジタル・ファースト・メディアのアドバイザリー・ボードのメンバーも務めるなど、メディア、ジャーナリズム業界でもっとも信頼が高いと評される人物です。
本書の原題を邦訳すれば「オタクたちの(作り出す)贈り物(恩恵)」という意味です。ジャービスは、本書の中で未来について語っているのですが、それは未来予想することや未来図を描くことではありません。
私が本書を読もうと思ったのは、本書がジャービスの本業のテーマであり、常に新しいテクノロジーやサービスへの探究心を持っていることに加え、彼が米国でも昔を懐かしみ現状を憂いて嘆くメディア関係者やジャーナリストがいるなかで、そのまなざしが下記のように未来に向けられているからです。
「私はとにかく未来に目を向けたい。少なくとも、未来にどのような可能性があるのかを知っておきたい。」
しかし、ジャービス自身も、誰にも未来がどうなるのかはわからないと率直に吐露しています。
ですから、もしこれからのメディアやジャーナリズムのあり方について、本書にその回答を性急に求めようとするのであれば、それは無駄に終わるでしょう。
現在の問題点、今後どのようなビジネスチャンスがあり得るのか、いくつかの提言をして読者とともに考えることが目的です。
3部構成、全26章、420ページ越えの力作

第一部(関係=Relationships)では、米国でも、メディアとジャーナリズム業界において、従来のビジネスモデルの崩壊、競争の激化、報道への信頼性の低下という「三重苦」は、いまの我が国と同様です。
ジャービス自身、これまでにも様々なレガシーメディアに関わってきましたし、かつては新聞や雑誌をいくつも購読していたのが、いまではそれらを読むことすらないそうです。
しかし、インターネット、ソーシャルメディアが殺したのはメディアではなく、「マス」というとらえ方(概念)そのものだと語ります。
さらに、ジャービスはニュースそれ自体が危機なのではなく、ニュースへのニーズはむしろ増えているし、共有する手段も豊富にある現在では多くの人たちの目に触れる機会は増えていると述べます。
要は、メディア企業が従来のやり方に固執し続けるかぎり、生き残ることは困難なだけだと。
ではどうすればよいのか。ジャービスは、そのために3つの提案をしています。
第一に、顧客となる人たちを「マス」と見なすことをやめて人間関係構築の技術を身につけること。第二に、ジャーナリズムもサービス業と考えること。第三に、市民とのネットワーク(コミュニティ)による多数のニュース発信による「ニュース・エコシステム」を構築すること。
上記の3つは、一般企業であればすでに当たり前のマーケティング戦略として取り入れていますが、旧態依然としてそれらすらできていないのがメディアやジャーナリズム業界なのだというのです。
ジャーナリストに求められているのは、市民の声を傾聴して主唱者となり、自らの信念や理念のため、市民の利益になることこそジャーナリズムであり、またジャービス自身は客観的で中立という神話(呪縛)から解き放たれるべきだと語ります。
そして最後に、「起業ジャーナリズム(アントレプレニュリアル・ジャーナリズム)を提唱しています。

第二部:形式の問題(Forms)では、これまでの記事に対する常識は捨てる覚悟を説きます。
記事こそが目的であり、作成して流せば終わりだった時代は終わり、これからの記事はサービスのツールであると発想し、個々に人々に最適な形式で提供するためにテクノロジーを駆使して読者を作ること必要があると語ります。
ツイッターを活用したニュースなどもありますが、玉石混淆の現在の環境では報道機関にもキュレーターの必要性があり、それは最良かつ最適(質、信頼性、目的など)であることが求められるのですが、ずるく稼ぐ安易な手口(一部のアグリゲーションやキュレーション)がはびこっているのは米国とて同様です。
だから、ジャーナリストの役割として、ツイッターなどの「報道」についてその正確性を判断するする目利き、玉石混淆の情報を適切に取捨選択しまとめる真のキュレーターが求められているし、それこそがジャーナリズムの担うべきことの1つだとジャービスは考えています。
だからこそ、ジャーナリストは社交的でコミュニケーション能力に秀でているべきだと。
キュレーションは、情報洪水社会にあってコンテンツの発見をもたらすからです。
また、オープン・ジャーナリズムを掲げる英「ガーディアン紙」の“ライブブログ”のような新しい試みに挑戦しているメディア、Wikiのニュースメディアの可能性、疑問や質問だけに答える特化型ニュースサイトなど、豊富に紹介される事例はヒントとなるでしょう。
また、モバイルのアプリ開発のほとんどは自己満足でしかないと指摘し、モバイルに対応するというのは、コンテキストに沿うことで、ユーザーのそのときの状況に最適な形(form)で提供することだと語ります。
単独メディア、1つのサイト、一つのアプリに過剰な期待はするなと忠告しています。
さらに、「炎上」や「荒し」行為を根絶するのは不可能だろうが、それでもオンラインでのコミュニケーションを無意味だとジャービスは考えていません。
メディア企業も、人々が情報共有しあえるプラットフォームビジネスに移行すべきで、それは人間関係を基礎としたものでなければならないし、それは「ニュース・エコシステム」をとしても構築されなければならないと強く主張しています。
後編では、本書の中心課題で邦題にもなっている「ジャーナリズムは稼げるか」(儲けられるかではないことに注意)について述べます。
関連記事:【書評】デジタル・ジャーナリズムは稼げるか〜メディアの未来戦略)<後編>