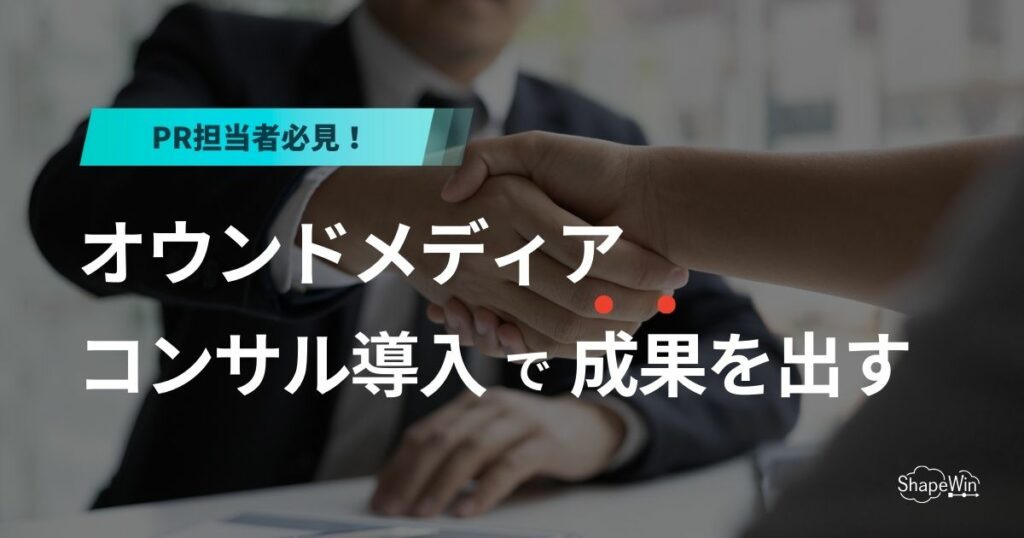検索経由で情報を得ることが当たり前となった今、オウンドメディアは企業のマーケティングや広報活動において重要な役割を担っています。しかし、多くの企業が取り組むWEBにおいて、自社メディアを埋もれさせず成果につなげるには、単に記事を更新するだけでは不十分です。
AIやツールを活用して安価に記事を量産する会社も増えましたが、多くはGoogleに評価されやすい“検索エンジン向け”のコンテンツにとどまります。そのような記事は、結局のところ読者の心を動かすことは難しく、トラフィックが増えても、最終的な目標である「問い合わせ」や「ブランド認知」につながらないのが現状です。
だからこそ、オウンドメディアを本当のビジネス資産に育てるには、事業理解とブランディング視点を持ったコンサルタントの存在が欠かせません。メディア全体の戦略を設計し、編集・広報・PRまで含めた一貫した支援ができる体制こそが成果を左右します。
この記事では、オウンドメディアコンサルが担う役割や依頼するメリット、失敗しない会社の選び方、そして企業が今注目すべき活用方法までを詳しくご紹介します。
オウンドメディアコンサルの4つの仕事・役割

オウンドメディアコンサルの役割は、単に記事制作を代行することではありません。
戦略設計からコンテンツ、SEO対策、SNS運用、広報・PR施策までを一気通貫で支援し、ビジネスの目的達成に直結する施策を伴走型で提案・実行していくのが特徴です。トラフィックだけでなく、ブランド価値やコンバージョンに繋げるための土台づくりを担います。
それではまず初めに、オウンドメディアコンサルタントの仕事・役割について詳しく解説していきます。
①戦略設計
目的やターゲットが曖昧なまま記事を発信しても、流入数や問い合わせ数にはつながりません。だからこそ、最初に明確なゴール設定と、その達成に必要な導線設計を行うことが重要です。
戦略設計では、企業の事業目標やブランドの強み、ユーザーが抱える課題を深く掘り下げた上で、「なぜオウンドメディアを運用するのか」という本質的な問いに立ち返ります。そのうえで、サイト全体の構成やコンテンツの切り口、更新体制、KPIなどを明文化し、運用フェーズに進みます。
加えてBtoBかBtoCか、商品・サービスの認知度、競合の発信状況などにより、戦略の方向性は大きく変わります。たとえばBtoBの場合は、ホワイトペーパーや事例コンテンツが効果的ですが、BtoCではSNSと連動した企画型コンテンツの方が反応が得られやすいです。
このように、オウンドメディアの目的や特性に応じた戦略設計が、すべての施策の土台となります。表面的な集客施策ではなく、成果につながるメディア運用には、精度の高い戦略立案が求められます。
②SEO・コンテンツ戦略
ユーザーにとって有益な情報を届けるためには、SEOの知見を活かしたコンテンツ戦略が欠かせません。単に検索上位を狙うだけではなく、検索意図を正確に捉え、読者の行動変容を促すコンテンツが必要です。
オウンドメディアコンサルでは、まず狙うべきキーワード群の調査から始めます。検索ボリュームや競合状況、CPC、検索意図の種類などを総合的に分析し、優先順位をつけてコンテンツの企画を行います。また、SEO視点に偏りすぎないことも重要で、専門性や信頼性、独自性(E-E-A-T)を意識した編集方針が求められます。
さらに、単発のコンテンツ制作ではなく、サイト全体として網羅性と内部リンクの導線設計があるかどうかも鍵を握ります。記事同士が連携し、ユーザーが自然とCVページにたどり着くような設計があることで、SEO効果とビジネス成果の両立が可能になります。
SEOに強いだけでなく、ユーザーにとって価値ある情報を発信できる体制づくりこそ、オウンドメディアの本質です。検索順位だけに頼らず、読まれ、信頼され、選ばれるメディアへと育てていく必要があります。
③メディア戦略
現代のコンテンツマーケティングでは、オウンドメディアだけではなく、SNSやニュースレター、外部メディアとの連携など、多角的なチャネル戦略を設計することが求められます。
特に立ち上げ初期のフェーズでは、Googleに評価されるまで時間がかかるため、SNSでのコンテンツ拡散やメールマーケティングなどでの認知獲得が重要になります。加えて、業界メディアやアーンドメディア(他社記事・取材)との連携により、信頼性の高いトラフィックを獲得できるのもポイントです。
このように、メディア戦略を立体的に設計することで、トラフィックの多様性が生まれ、特定チャネルに依存しない強いメディアが育ちます。広報・PR、SNS運用、広告運用といった外部との接点も視野に入れ、全体を統合的に設計できるのがコンサルの強みです。
多角的なメディア戦略については以下の記事を参照ください
トリプルメディアの仕組みとPESOモデルの違い
分析とレポート
最後に、メディア運用の改善に欠かせないのが、数値に基づく分析とレポートです。どのコンテンツが読まれ、どのチャネルが有効で、どこに離脱ポイントがあるのか。これらを可視化し、次の打ち手につなげることがコンサルの重要な役割です。
たとえば、GoogleアナリティクスやSearch Console、SNSインサイトなどのツールを用いて、流入経路、回遊率、CV率、滞在時間などを定点観測します。また、コンテンツごとの読了率やスクロール率、SNSでのシェア数も、改善のヒントになります。
コンサルティングでは、ただ数値を報告するのではなく、「なぜその数値になったのか」「次に何をするべきか」まで言語化して共有します。これにより、社内でも改善意識が高まり、関係者が同じ目線でPDCAを回せるようになります。
オウンドメディアコンサルを依頼する4つのメリット

オウンドメディアは「立ち上げれば成果が出る」というものではありません。
むしろ、自社のリソースだけで企画・制作・運用・改善まで行うには、非常に高い専門性と継続的な労力が求められます。そこで、戦略から施策実行まで一気通貫でサポートできるオウンドメディアコンサルに依頼することは、費用対効果の面でも大きなメリットがあります。
では、具体的にどのようなメリットがあるのか、4つの観点から見ていきましょう。
①リソースの削減
オウンドメディアの運用は、想像以上に多くの工数を要します。
企画立案、コンテンツ制作、SEO設計、進行管理、効果測定など、多岐にわたるタスクを社内で完結させるには、専門性とマンパワーの両方が必要です。特に中小企業では、マーケティング専任の担当者がいない場合も多く、片手間で対応してしまうと結果が出にくく、むしろ遠回りになってしまうことも少なくありません。
オウンドメディアコンサルに依頼すれば、戦略策定から実務まで外部に任せることができ、社内の工数を大幅に削減できます。加えて、全体設計や成果指標に基づいた効率的な運用が可能になるため、リソースを無駄なく活用できます。
限られた人員でも成果を出したい企業にとって、非常に現実的な選択肢です。
②専門的な視点で戦略が立てられる
オウンドメディアをいざ自社で立案しようとすると、客観性や業界知識が足りず、曖昧な目的のままスタートし、結局人件費の無駄遣いになってしまうことがあります。
特に、SEOやコンテンツマーケティング、SNSとの連携など、専門知識を要する分野では判断が難しいものです。
オウンドメディアコンサルは、第三者の視点から自社の状況を正確に把握し、戦略を言語化・設計してくれます。市場や競合を踏まえた上でのポジショニング、ユーザー理解に基づいたコンテンツテーマ設計など、事業成果につながる土台を構築できます。
こうした専門的な知見は、外部のプロに依頼するからこそ得られるものです。
③安定的な高品質コンテンツの作成
オウンドメディアにおいて、継続的に質の高いコンテンツを発信し続けることは、ブランディングにもSEOにも直結します。
しかし、社内でライティングのスキルを持つ人材が限られている場合、制作のたびに外注を検討したり、品質のバラつきが発生することもあるでしょう。
オウンドメディアコンサルに依頼することで、経験豊富なライターや編集者、ディレクターがチームで関与し、読者の行動変容を促すコンテンツを安定的に提供することが可能になります。特に、企業の専門性や文脈を踏まえたストーリーテリング型の記事は、読者の心に残りやすく、信頼感の醸成にも繋がります。
単なるSEO対策記事ではない、“伝わるコンテンツ”を定期的に制作できる体制は、大きな強みになります。
④成果につながる
オウンドメディア運用の最終的な目的は、トラフィックではなく「成果」を出すことです。
いくらアクセス数が増えても、問い合わせや資料請求といったコンバージョンに繋がらなければ、投資対効果としては十分とは言えません。
オウンドメディアコンサルは、ビジネスの目的から逆算してコンテンツ設計を行い、ユーザーの関心フェーズに合わせて導線を設計します。例えば、見込み顧客の検討段階に応じたホワイトペーパーや事例記事を用意し、スムーズなナーチャリングを図るなど、成果に直結する仕組みを組み入れます。
トラフィック獲得だけで満足していないか、改めて自社のメディア運用を見直すタイミングかもしれません。コンバージョンまで見据えた設計は、プロによる支援だからこそ実現できます。
オウンドメディアコンサル会社の選ぶ5つのポイント

オウンドメディアの成果は、どのコンサル会社と組むかによって大きく変わります。SEOだけが強い会社、記事だけを書ける制作会社、PRだけに特化している会社など、どれも一長一短で、目的に応じた会社選びができなければ、効果は限定的になってしまいます。
だからこそ、技術と編集、広告と広報、すべての領域を横断的に理解している“チーム力”が求められます。
ここでは、失敗しないためのコンサル会社選びの視点をご紹介します。
①テクニカル、マスメディア両方のプロが在籍しているか
成果を出すためには、SEOやCMSのようなテクニカルな領域と、メディア視点での編集力やストーリーテリングのような“伝える力”の両方が必要です。片方だけでは、アクセスは集まっても心を動かすことができなかったり、ブランディングとして不十分になったりします。
例えば、Googleのアルゴリズムに最適化された記事でも、そこに企業の強みや価値観が反映されていなければ、読者の記憶には残りません。その点、テクニカルとマスメディア両方の専門家が連携しているチームであれば、企業の個性を活かしつつ、検索上位にも対応できる「成果が出る記事」を設計できます。
コンサル会社を選ぶ際は、どちらの視点にも精通しているかを見極めましょう。
②分野での実績・理解があるか
どれほど実績が豊富な会社であっても、自社と無関係な業界ばかり対応している場合は注意が必要です。
たとえば、医療、製造業、SaaS、自治体など、それぞれの業界には特有の言葉選びや配慮すべきポイントがあります。業界への理解が浅いままでは、見当違いのトーンやテーマになり、ターゲットに刺さらないコンテンツになってしまう可能性もあります。
選定時には、事前に「自社の業界に近い事例があるか」「記事内容に専門性を感じるか」を確認するとよいでしょう。専門性と読みやすさを両立できているかどうかも判断基準となります。
③円滑なコミュニケーションが取れるか
オウンドメディアは一度立ち上げて終わりではなく、半年〜数年単位で伴走していく取り組みです。
だからこそ、担当者との意思疎通がスムーズかどうかは非常に重要なポイントです。要望をしっかりヒアリングしてくれるか、専門用語ばかりでなく丁寧に説明してくれるか、進行管理やレスポンスが的確か。これらは実務面での信頼感に大きく影響します。
実際に話してみて、「この人たちとなら一緒に進められる」と思えるかどうかは、コンサルの成果を左右する重要な判断材料です。
④質の高いライターを揃えているか
どれだけ戦略が優れていても、実際にユーザーに届くのは「記事そのもの」です。つまり、ライターの質はメディアの質に直結します。Googleに好かれる文章ではなく、読者に読まれ、共感され、行動に繋がる文章を書くには、ストーリーテリングや編集力が求められます。
特に企業ブランディングを重視する場合、ただのキーワード記事ではなく、企業の背景や想い、社会的な意義などを伝える文章力が不可欠です。
シェイプウィンでは、有名メディアで実績を持つライターが在籍しており、PR文脈を理解したライティングが可能です。ストーリーテリングに強いライターが書くからこそ、読者の感情に訴える記事が実現します。
ライターのクオリティは、コンサル会社選びの大きな差別化要因になります。
⑤オウンドメディアだけでない他のメディアの知識があるか
オウンドメディア単体では、どうしてもリーチに限界があります。SNS、メールマガジン、外部メディア、プレスリリースなど、複数のチャネルを組み合わせることで、ようやく“伝わるメディア”が完成します。
そのためには、他メディアの特性を理解したうえで連携戦略を組めるコンサル会社であることが重要です。PRや広告の知見がある会社であれば、記事を露出させるための導線づくりまでサポート可能です。メディアごとに役割を整理し、オウンドメディアに最適なトラフィックを流し込む設計ができるかどうかが、成果に直結します。
オウンドメディアを“事業の一部”として本当に機能させたいなら、全体最適の視点を持つパートナーを選ぶべきです。
おすすめの使い方
オウンドメディアコンサルを最大限に活用するためには、単なる「外注」ではなく、自社のフェーズや課題に合わせた“使い方”を設計することが鍵となります。
目的が明確でないまま進めると、期待していた成果に届かないことも少なくありません。ここでは、特に成果に直結しやすい3つの活用方法をご紹介します。
戦略設計から依頼する

オウンドメディアを始めるにあたって最も重要なのが、「なぜやるのか」「誰に向けて何を届けるのか」という戦略設計です。ここが曖昧なままスタートすると、記事を重ねても効果が見えず、途中で頓挫してしまうケースが多く見られます。
その点、プロのコンサルタントに戦略設計を依頼すれば、自社の事業やブランドのポジショニングを客観的に分析し、最適なコンセプトやターゲット設定を行ってくれます。媒体のトンマナ(トーン&マナー)やカテゴリ設計まで一貫して設計することで、継続的に意味のある発信が可能になります。
無駄な工数やコンテンツ制作のやり直しを防ぐためにも、最初の戦略フェーズだけでもプロに依頼するのがおすすめです。
リブランディングのきっかけにする

自社の強みや社会的な意義を新しい視点から再編集し、信頼性の高いメディアを通じて届けることで、企業の姿勢そのものをブランドとして確立することができます。
例えば、以下の記事のように専門的な切り口を用いたコンテンツは、業界内の信頼を得るだけでなく、新たな認知を広げるブランディング施策の例です。
https://staff.persol-xtech.co.jp/i-engineer/technology/stradvision
このように、単にSEOに寄せた記事ではなく、読者の行動や感情を動かす「ストーリー」を持っている点です。こうした視点でオウンドメディアを見直すことで、単なる情報発信から脱却し、企業の姿勢や文化を語るブランド効果も期待することができます。
結果として、社内外のステークホルダーとの信頼関係も強化され、オウンドメディアが単独で事業の一つとして機能する可能性も広がっていきます。
コンテンツ作成は内製化を目標にする
継続的な発信を見据えると、最終的にはコンテンツ制作を内製化していく体制づくりも重要になります。
理想は、コンサル会社に伴走してもらいながら、社内メンバーが徐々にライティングや編集のスキルを身につけていくスタイルです。
記事構成案の作り方、見出しの設計、読者導線の考え方など、運用ノウハウを社内に移管していくことで、将来的にはコストを抑えつつ、自社の世界観を深く伝えられるチームを育てることができます。
“育成を前提とした支援”を行ってくれるコンサル会社を選べば、短期的な成果だけでなく、長期的なブランド資産の構築にもつながります。
まとめ:PR視点を持った戦略設計が重要

オウンドメディアは単に記事を発信する場ではなく、企業の信頼やブランド価値を築くための「戦略的な資産」です。
しかし、トラフィックを集めるSEO記事だけでは、実際の成果にはつながりにくい時代となりました。今求められるのは、読み手の行動を変えるストーリーテリングや、SNSやPRを含めた多面的な発信です。
とはいえ、自社でこれらを網羅するのは現実的ではありません。だからこそ、広報PR視点と戦略企画を兼ね備えたオウンドメディアコンサルが必要とされています。
シェイプウィンは、日本ではまだ少ない「PR会社によるオウンドメディア支援」を行っているチームです。単なるSEO代行ではなく、行動変容を促すストーリー設計と広報・マーケティングの連携によって、御社の価値を社会に届ける支援を行います。まずはご相談からお気軽にご連絡ください。