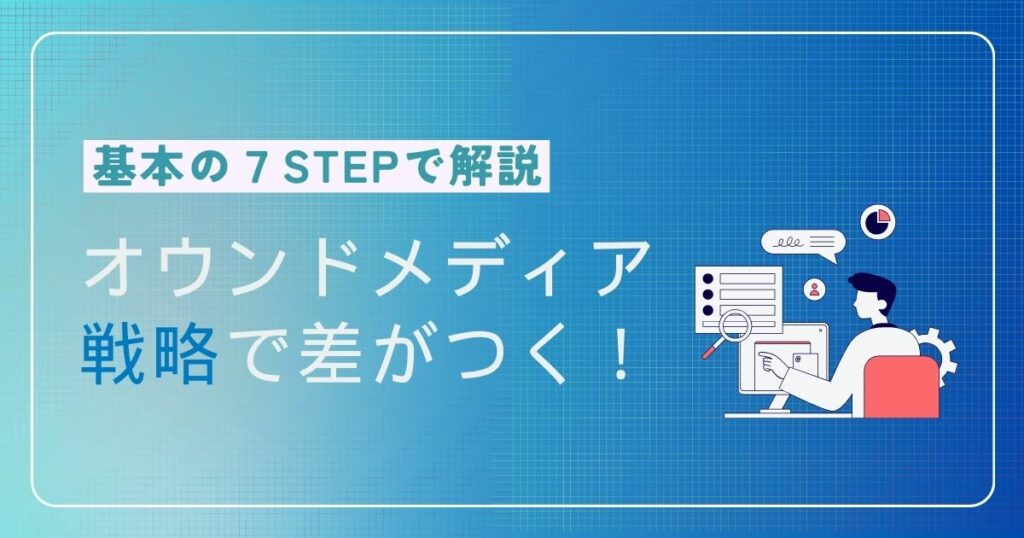「オウンドメディアを立ち上げたものの、思うような成果が得られていない」そんな悩みを抱えるWeb担当者は少なくありません。
検索からの流入を狙ったSEO対策ももちろん重要ですが、それだけでは企業の想いや価値まで伝えることは難しいのが現実です。現代ではSNSも重要なコンテンツにはなっていますが、SNSは顧客の注意を引くことを得意としているので、その後により深く会社について知ってもらいお問い合わせに繋げることが必要となります。
そこで重要になるのが、最終的に深い理解や信頼を築く場として、オウンドメディアを単に運営するのではなく、戦略設計が果たす役割はますます大きくなっています。
そこで本記事では、成果につながるオウンドメディア戦略の立て方を、ステップごとに詳しく解説していきます。
オウンドメディア戦略の重要性

オウンドメディアの成果を最大化するためには、目的に応じた明確な戦略設計が不可欠です。
リード獲得やブランディングといった目的に対して、どのようなステップでどのチャネルを使うべきかを明文化しない限り、継続的な集客や認知拡大にはつながりません。
ここではまず、「そもそも何のためにオウンドメディアを運用するのか」という基本的な視点から、目的と戦略の関係性について掘り下げていきます。
オウンドメディアの目的とは?
オウンドメディアの目的は、リード獲得やブランディングといったマーケティング成果を中長期的に実現するための「戦略的な情報発信の土台」を構築することにあります。単なるブログ運用ではなく、事業目標に直結した集客と信頼の獲得が本質です。
たとえば、BtoB企業であれば見込み顧客との接点づくりやナーチャリングが主目的になります。一方でBtoCの場合は、商品やブランドの世界観を伝え、共感を得るブランディングが重要な役割を担います。さらに近年では、オウンドメディア自体を収益化し、メディア事業として展開するケースも増えてきました。
こうした目的に応じて、戦略の立て方やコンテンツの切り口、集客チャネルの設計も大きく変わってきます。リード獲得を目指すならSEOを軸にしつつ、ホワイトペーパーや導線設計が重要になりますし、ブランディング重視であればSNS連携やストーリーテリング型のコンテンツが効果的です。
つまり、オウンドメディアとは「誰に・何を・なぜ届けるのか」という目的設計から始まるべきものであり、それが明確になって初めて、KPIや運用体制の整備、チャネル選定といった実践的な設計へと落とし込むことが可能になります。
オウンドメディアの効果
オウンドメディアは単なる“情報発信の場”ではありません。コンテンツを通じて、見込み顧客との関係性を深め、ブランドの価値を伝えることができる、極めて戦略的なマーケティング手法です。
近年、国内外で注目されているのが「コンテンツを通じて信頼を築く」PR手法としての活用です。検索エンジンやSNSでは見つからない“自社独自の視点”を語ることで、他社との差別化が可能になります。
オウンドメディアにはさまざまな形式があります。たとえば、複数の特集コーナーを持つ企業メディア、専門家によるナレッジ共有ブログ、採用広報を目的としたインタビューメディアなどです。自社のリソースや目的に応じて、柔軟に設計・運用することができます。
この柔軟性こそ、オウンドメディアが他の広告媒体やSNSと異なる強みです。また、コンテンツは資産として残り続けるため、積み重ねるほどに効果が増していく“ストック型の集客チャネル”でもあります。
つまり、オウンドメディアは単なる集客手段ではなく、ブランディングとリードジェネレーションの両面から長期的に企業の価値を支える土台となります。戦略的に設計すれば、メディア自体が新たな事業の柱になる可能性もあるのです。
オウンドメディア戦略設計の7ステップ

オウンドメディアを成功させるには、「戦略設計」が欠かせません。行き当たりばったりの運用では成果は出にくく、目的や運用体制、コンテンツの設計まで一貫して構築する必要があります。ここからは、戦略設計における基本ステップをご紹介します。
①目的を明確にする

オウンドメディア戦略の第一歩は、目的の明確化です。何のためにメディアを運用するのかが曖昧なままでは、どれだけ記事を重ねても成果にはつながりません。
目的には、リード獲得・ナーチャリング、認知拡大、ブランディング、メディアの事業化などさまざまな種類があります。たとえば、見込み顧客を集めたい場合はSEOによる検索流入を確保する必要がありますが、それだけでは企業の世界観や思想を伝えきれないことも。だからこそ、ストーリーテリング記事のような深い情報設計が重要になります。
ストーリーテリング記事とは、事実やデータを羅列するだけでなく、企業のビジョンや人の声、実体験などを物語のように描くことで、読者に共感や信頼を与えるコンテンツです。商品・サービスの説明にとどまらず、企業そのものの姿勢や価値観まで伝えられるため、特にブランディングやファンづくりに効果的です。
また、運用フェーズによってはSNSや広告などのチャネルも活用し、マルチチャネルでの集客を設計しておくと効果的です。目標に応じて、流入経路やコンテンツの種類を柔軟に変えていきましょう。
②目的から成果(KPI)を決める

明確な目的を設定したら、それに応じたKPI(成果指標)を設計します。KPIがなければ、メディアの進捗や成果を測ることができず、改善の打ち手も定まりません。
例えば、「リード獲得」が目的であれば、資料請求数や問い合わせ件数がKPIになります。「ブランディング」が目的の場合は、SNSのエンゲージメントや指名検索数、滞在時間などが参考指標になります。
さらに、フェーズごとにKPIを切り替えることも重要です。立ち上げ初期は公開本数などの行動指標やPVを、中期以降はCVや滞在時間といった読者の行動変容に関する成果指標を追うのが基本です。目的と連動したKPIを設定することで、戦略と運用がブレずに進行できます。
どうしてる?オウンドメディアのKPIを徹底解説
③競合・ターゲットのリサーチ

戦略設計においては、競合とターゲットの深いリサーチも欠かせません。同じ業界の他社がどのような情報を発信しているか、どんなキーワードを狙っているかを分析することで、自社が狙うべきポジションが見えてきます。
また、ターゲット像が曖昧だと、誰に向けて何を届けるべきかがブレてしまい、発信に一貫性がなくなります。ペルソナの設計に加え、検索ニーズやSNSでの関心トピックなど、実際のユーザー行動を踏まえたリサーチを行いましょう。
市場や顧客を正しく理解することで、無駄のない戦略設計が可能になります。
④サイトコンセプトの設計

メディア全体の印象や価値を決めるのが、サイトコンセプトの設計です。ここで重要なのは、単なるビジュアルではなく「どんな目的で、誰に、どんな価値を提供するメディアなのか」を言語化することです。
たとえば、「働き方改革に取り組む企業向けの情報を発信する」や、「若手エンジニアのキャリア形成を支援する」といった、軸のあるコンセプトがあれば、コンテンツ制作もぶれずに進めることができます。
この段階でトンマナ(トーン&マナー)やカテゴリ構成なども決めておくと、社内外のライターへの共有もしやすくなり、運用の一貫性が保てます。
⑤運用体制を整える

設計段階だけでなく、「誰が、何を、どこまで担うのか」を整理した運用体制の構築も非常に重要です。
記事の企画、執筆、編集、公開、分析まで、一連の工程には多くのタスクが発生します。社内でどこまで対応できるか、外部パートナーに依頼する範囲はどこかを明確にしておくことで、スムーズな運用が可能になります。
特にリソース不足が予想される場合は、最初からコンサルティングや編集代行など、プロに頼る前提で体制を設計することも選択肢の一つです。
⑥運用計画・戦略を立てる

いざメディアを立ち上げても、継続的に成果を出すには運用計画が必要不可欠です。計画が曖昧だと、更新が止まったり、企画の方向性がずれたりといったリスクが高まります。
運用計画では、投稿頻度やテーマ、記事の役割(集客/CV獲得/関係構築)を明確にし、編集会議などのフローも設けることで、PDCAを効率的に回すことができます。
また、ここで「メディア戦略」も同時に設計しておきましょう。SNS、メルマガ、広告など、オウンドメディアだけに依存しない流入元を複数確保しておくことで、安定した集客基盤を築けます。
⑦効果測定と改善

最後に欠かせないのが、運用結果の効果測定と改善です。定期的にKPIをチェックし、どの施策が成果につながったのかを分析することで、メディアの精度が上がっていきます。
GoogleアナリティクスやSearch Consoleなどのツールを活用して、PV、滞在時間、CV率、検索キーワードなどの数値を把握しましょう。数値だけを見るのではなく、「なぜその結果になったか」をチームで共有し、次の施策へと活かすことが重要です。
改善サイクルを回せるかどうかが、長期的なメディアの成長を左右します。
オウンドメディア戦略立案時によくある失敗とお悩み

オウンドメディアは、戦略さえ立てれば成果が出るというものではありません。
多くの企業が、実際の運用フェーズで「想定通りに進まない」と感じています。その多くは、設計段階の見落としや、人的リソース、目標設定の甘さに起因しています。
ここでは、オウンドメディア戦略立案時によくある失敗事例とその解決策を紹介します。
運用リソース不足でコンテンツの質の確保が難しい
多くの企業がつまずくポイントは、「運用リソースの不足」です。
オウンドメディアの運用には、企画・執筆・編集・分析といった多くの作業が発生し、それを継続する体制が必要です。実際には、担当者が他業務と兼任していたり、コンテンツの質が安定しなかったりすることが頻繁に起きています。
さらに、社内メンバーだけで運用している場合、「ネタ切れ」や「発信の偏り」といった課題も出てきます。こうした悩みを解消するためによくあるのは、ブログ手当のような福利厚生制度の活用や、部署横断で執筆をリレー形式にするなどの工夫です。
それでも限界がある場合は、外注を検討するのもひとつの方法です。特に、戦略設計や編集のような専門的な領域は、最初からプロに任せることで、質とスピードを両立しやすくなります。
ターゲットが不明確だった
オウンドメディアで成果が出ない大きな理由のひとつが、「ターゲット設定の甘さ」です。
誰に向けて何を発信するのかが曖昧だと、コンテンツの内容もブレやすく、結果的に誰の心にも届かない記事になってしまいます。
たとえば、BtoB向けとBtoC向けでは、伝えるべき情報や文体、チャネル設計も大きく異なります。また、企業の規模や業種によっても抱える課題はさまざまです。
ターゲットを明確にするには、ペルソナ設計だけでなく、「その人がどんな検索行動をするか」「SNSではどんな情報を求めているか」など、ユーザーの行動背景を把握したうえで情報設計を行うことが不可欠です。
オウンドメディアは“誰にでも刺さる情報”ではなく、“誰か一人に確実に届く情報”を設計することが成功の鍵です。
短期的な計画だった
オウンドメディアは、即効性を求める施策ではありません。成果が出るまでには数ヶ月〜1年以上かかることもあり、継続的な運用が必要です。しかし、多くの企業が「3ヶ月で結果が出なかった」として更新をストップしてしまうケースが見られます。
この背景には、短期的な視点でKPIを設定してしまっていることや、事前に継続的なリソース計画がなかったことが挙げられます。
最初から1年程度の運用計画を持ち、「初期フェーズは認知獲得」「中期以降にリードの獲得やコンバージョンを目指す」といった段階的な目標設定をしておくことが重要です。
オウンドメディアは、“資産”として積み上げるマーケティング手法です。短期的な結果だけでなく、継続によるブランド構築や信頼醸成を視野に入れる必要があります。
KPIのたて方が間違っていた
戦略的に設計したはずのメディアがうまく機能しない理由として、「KPIの設定ミス」もよくあります。KPIは目的に応じて段階的に変化させるべきで、常にPV数だけを追いかけていても、真の成果には結びつきません。
たとえば、立ち上げ初期はPVやSNSシェア数といった“行動KPI”を設けて、まずは認知拡大を目指します。そして中期以降は、資料請求や問い合わせなどの“成果KPI”へと移行し、具体的なコンバージョン獲得を追う設計が必要です。
KPIが合っていないと、効果が見えずに社内評価が得られず、モチベーションの低下や施策の中断につながります。フェーズごとのKPIをしっかり見直し、目的との整合性を保ちながら運用していくことが大切です。
まとめ:時間がかかるからこそ、戦略設計が重要

オウンドメディアは成果が出るまでに時間がかかるからこそ、設計の段階でのつまずきが後々まで影響します。
KPI設定の甘さ、ターゲットの不明確さ、リソース不足など、失敗パターンは多くの企業で共通しています。しかし、戦略と運用を両立できる体制が整えば、メディアは事業の資産として確実に育っていきます。
シェイプウィンは、日本ではまだ少ない「PR会社によるオウンドメディア支援」を行っているチームです。単なるSEO代行ではなく、行動変容を促すストーリー設計と広報・マーケティングの連携によって、御社の価値を社会に届ける支援を行います。まずはご相談からお気軽にご連絡ください。